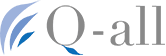被扶養者認定に関する通達等が発出されています
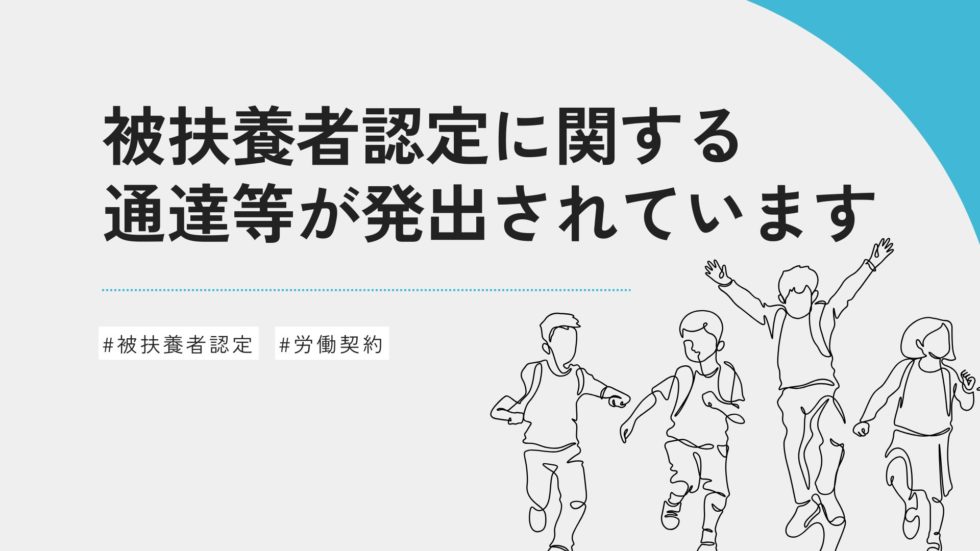
厚生労働省のデータベースに、「「年収の壁・支援強化パッケージ」における事業主の証明による被扶養者認定の円滑化の取扱いの恒久化について」(令和7年10月1日保保発1001第1号)、「労働契約内容による年間収入が基準額未満である場合の被扶養者の認定における年間収入の取扱いについて」(令和7年10月1日保保発1001第3号年管管発1001第3号)、「労働契約内容による年間収入が基準額未満である場合の被扶養者の認定における年間収入の取扱いに係るQ&Aについて」(令和7年10月1日事務連絡)が掲載されました。
次のような内容となっています。
「年収の壁・支援強化パッケージ」における事業主の証明による被扶養者認定の円滑化の取扱いの恒久化について
(令和7年10月1日保保発1001第1号)
当面の対応として「年収の壁・支援強化パッケージ 」に基づき実施している「事業主の証明による被扶養者認定の円滑化」を、恒久的な取扱いとされます。
具体的な運用については「「年収の壁・支援強化パッケージ」における、社会保険適用促進手当の標準報酬算定除外及び事業主の証明による被扶養者認定の円滑化の取扱いについて」(令和5年10月20日付け保保発第3号厚生労働省保険局保険課長通知。同年12月25日一部改正)によるとされています。
労働契約内容による年間収入が基準額未満である場合の被扶養者の認定における年間収入の取扱いについて
(令和7年10月1日保保発1001第3号、年管管発1001第3号)
令和8年4月1日から労働契約内容によって被扶養者の年間収入を判定することとしてその取扱いを整理されました。
労働契約で定められた賃金(諸手当および賞与も含む)から見込まれる年間収入が130万円未満であり、かつ、他の収入が見込まれず、下記に該当する場合には、原則として、被扶養者に該当するものとして取り扱うこととされました。
(1)認定対象者が被保険者と同一世帯に属している場合には、被保険者の年間収入の2分の1未満であると認められる場合
(2)認定対象者が被保険者と同一世帯に属していない場合には、被保険者からの援助に依る収入額より少ない場合
労働契約の内容によって被扶養者の認定を行う場合は、労働条件通知書等の賃金を確認し、年間収入が130万円未満である場合には、原則として被扶養者として取り扱うこととなりました。
なお、労働契約の更新が行われた場合や労働条件に変更があった場合には、当該内容に基づき被扶養者に係る確認を実施することとし、条件変更の都度、当該内容が分かる書面等の提出を求められます。
被扶養者認定の適否に係る確認時において、当初想定されなかった臨時収入により、結果的に年間収入が130万円以上の場合であっても、当該臨時収入が社会通念上妥当である範囲に留まる場合には、これを理由として、被扶養者としての取扱いを変更する必要はないとされました。
給与収入以外に他の収入(年金収入や事業収入等)がある場合における当該給与収入を含む年間収入の取扱いについては、従前のとおりの取扱いとされます。
船員保険法2条9項各号に規定する被扶養者の認定についてもこれに準じて取り扱いが行われます。
労働契約内容による年間収入が基準額未満である場合の被扶養者の認定における年間収入の取扱いに係るQ&Aについて
(令和7年10月1日事務連絡)
Q1 労働契約内容によって年間収入を判定することにした趣旨如何。
➤認定対象者の年間収入については、認定対象者の過去の収入、現時点の収入または将来の収入の見込みなどから、所定外賃金の見込みを含めた今後1年間の収入見込みにより判定をしているところですが、就業調整対策の観点から、被扶養者認定の予見可能性を高めるため、労働契約段階で見込まれる収入を用いて被扶養者の認定を行うこととしたものです。
そのため、労働契約に明確な規定がなく労働契約段階では見込み難い時間外労働に対する賃金等は、被扶養者の認定における年間収入には含まないこととなります。
Q2 労働契約で定められた賃金から見込まれる年間収入が130万円未満であるとは、具体的にどのような場合か。
➤労働条件通知書等の労働契約の内容が確認できる書類において規定される時給・労働時間・日数等を用いて算出した年間収入の見込額が 130 万円未満である場合を想定しています。
そのため、当該書類上に明確な規定がなく予め金額を見込み難い時間外労働に対する賃金等は年間収入の見込額には含まないこととなります。
Q3 労働契約内容が確認できる書類がない場合、どのように年間収入を判定するのか。
➤労働契約内容が確認できる書類がない場合は、従来どおり、勤務先から発行された収入証明書や課税(非課税)証明書等により年間収入を判定することとなります。
Q4 労働契約に明確な規定がなく労働契約段階では時間外労働の見込みがなかったが、扶養認定時点では経常的に時間外労働が発生している場合は、どのように年間収入を判定するのか。
➤労働契約に明確な規定がなく労働契約段階では時間外労働の見込みがなかったのであれば、扶養認定時点で時間外労働が発生していたとしても、当年度においては一時的な収入変動とみなし、今回の取扱いにより年間収入を判定することとなります。
Q5 認定対象者の「給与収入のみである」旨の申立てはどのように求めるのか。
➤健康保険被扶養者(異動)届の「扶養に関する申立書」欄に認定対象者本人が記載する方法や、健康保険被扶養者(異動)届の添付書類として認定対象者本人が作成した「給与収入のみである」旨の申立書を添付させる方法等により対応を行ってください。
Q6 給与収入以外に他の収入(年金収入や事業収入等)がある場合、年間収入はどのように判定するのか。
➤従来どおり勤務先から発行された収入証明書や課税(非課税)証明書等により年間収入を判定することとなります。
Q7 被扶養者の認定の適否に係る確認について、どのように実施すべきか。
➤認定年度において被扶養者の認定の適否に係る確認を行う必要はないですが、翌年度以降少なくとも年1回は保険者において被扶養者の認定の適否に係る確認を行い、被扶養者の要件を引き続き満たしていることを確認してください。
なお、被扶養者の認定の適否に係る確認においても、認定時と同様に労働条件通知書等の労働契約内容が確認できる書類を確認することにより実施しますが、労働契約の内容が確認できる書類が存在しない場合には従来どおり勤務先から発行された収入証明書や課税(非課税)証明書等を確認することにより実施します。
また、労働契約内容が確認できる書類により認定の適否の確認を実施する場合においても、実際の年間収入との乖離を確認するために勤務先から発行された収入証明書や課税(非課税)証明書等の提出を求めても差し支えありません。
Q8 被扶養者の認定後、被扶養者の認定の適否に係る確認において、勤務先から発行された収入証明書や課税(非課税)証明書等により、臨時収入によって結果的に年間収入が130万円以上となっていることが判明した場合は、被扶養者の認定を取り消すのか。
➤被扶養者の認定の適否に係る確認時において、被扶養者の認定段階で見込んでいなかった臨時収入によって結果的に年間収入が130万円以上となった場合であっても、当該臨時収入が社会通念上妥当である範囲に留まる場合には、これを理由として、被扶養者の認定を取り消す必要はありません。
一方で、当該臨時収入により実際の年間収入が社会通念上妥当である範囲を超えて 130 万円を大きく上回っており、労働契約内容の賃金を不当に低く記載していたことが判明した場合には、被扶養者に該当しないものとして取り扱って差し支えありません。
なお、当該臨時収入が一時的な収入変動かどうかの確認のために「年収の壁・支援強化パッケージ」における事業主証明の提出を求めても差し支えありません。
Q9 本通知による取扱いは令和8年4月1日から適用とのことだが、認定日を基準として取り扱うことで良いか。
➤お見込みのとおりです。本通知による取扱いは、認定日が4月1日以降となるものについて適用されます。なお、令和8年4月1日より前に遡って認定する場合は、従来の取扱いにより判定することとなります。
詳細は、下記リンク先にてご確認ください。
被扶養者認定 年間収入要件 被扶養者 労働契約 労働条件通知書 賃金 給与
「年収の壁・支援強化パッケージ」における事業主の証明による被扶養者認定の円滑化の取扱いの恒久化について(令和7年10月1日保保発1001第1号)
労働契約内容による年間収入が基準額未満である場合の被扶養者の認定における年間収入の取扱いについて(令和7年10月1日保保発1001第3号年管管発1001第3号)
労働契約内容による年間収入が基準額未満である場合の被扶養者の認定における年間収入の取扱いに係るQ&Aについて(令和7年10月1日事務連絡)
人事・労務関連のお悩みやお手続きは、社会保険労務士法人Q-allへお任せください
私たちは企業が活動していく上で必要な3要素である「ヒト」「モノ」「カネ」のうちの、「ヒト」の問題に関するプロフェッショナルです。
給与計算や従業員の雇用や退職で発生する保険関係等のお手続きをはじめ、職場で発生するさまざまな労働問題のコンサルティング等を行うほか、公的年金に関する唯一の国家資格者として年金に関する相談にも応じ、雇用や労働にまつわる問題を幅広く取り扱っています。また、それに付随する就業規則の作成や36協定等の労使協定の整備など、人事・労務管理のあらゆる業務をトータルサポートさせていただきます。
社会保険労務士は唯一法律で助成金の申請代行が許されており、その中でもQ-allはこれまでの助成金申請件数が7000件を超えるなど、豊富な実績があり、万全のサポート体制で申請・受給までのお手伝いをしております。また、助成金受給率は99%以上、累計受給額は26億円以上と、助成金にも力をいれておりますので、助成金に関する柔軟な対応も可能となっております。
担当者の急な退職・休職でお困りの方、人事・労務管理のアウトソーシングをお考えの方、助成金申請をお考えの方、ぜひお気軽にご相談ください。
❀ご興味のある方は、下記よりお問い合わせくださいませ。
お問い合わせ |社会保険労務士法人Q-all
今後も助成金に関する緊急速報をアップさせていただきます。
その他、弊社のYouTubeチャンネルにも助成金や労務管理に関する様々な情報を公開しておりますのでよろしければぜひ一度ご覧ください☆
✯YouTubeチャンネルはこちら!↓↓
https://www.youtube.com/@henmichannel/featured